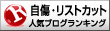[15]心の傷(8)
立ち上がった、のは良いもののここからどうしようか。涙が枯れた頬は少しばかり肌寒く、一番奥のトイレに入ったので窓を開け、まだ少し寒い風にあたりながらただボーっと外を見ていた。
普通に戻って行く?そしたらきっと「何していたの」と聞かれる、答えることは出来ない。友人に泣いたことを話すなんて、絶対にしては行けない。私は大層な強がりで、小学生の時手首の骨を骨折しても涙を堪え泣くことはなかった。唯一泣いたのはプールで転んで足を捻挫したときだけ。あの痛みには堪えることができずつい「痛ぇ!」と泣いてしまった。勿論、初めて私の涙を見た友人たちはたったこれだけでも驚いていた。そんな涙知らずな私がトイレで一人篭って泣いてました?だなんて自分の情けない姿を晒すことはできない。
そう考えたらトイレから出れなくなってしまった。どうせならこのまま放課後まで居座ってしまおうか。
教室に居る生徒は給食の時間、初めての新しい友達との昼飯を楽しんでいる、そんな声が聞こえてくる。トイレの時間だけはとても無機質で、灰色の壁と肌寒い風が少しばかりか寂しく思えた。そんな気持ちに首を振って、また私は膝を落とした。動くのが面倒だ。私の口癖は「めんどくせー」なのだから、授業めんどくさかったからということにすれば良い。
半ば投げやり状態に考えてはいたものの、誰か助けてほしいと思ってしまう自分が情けなくて私はまた目を閉じてしまった。
「いるか?」私は直ぐに顔を上げた。この声は先生の声だ。きのっちが来た。私は「います」と答えて身体を起こした。大丈夫、声は震えていない。先生が「入るぞ」と女子トイレの暖簾を潜ってきた。足音が近づいてくる、私は動揺することなく閉めているドアに視線を向けていた。先生がドアの前に来た。「どうした?」と聞かれた。私は黙った。先生は「さっきの事か?」と聞いた。
私はしゃくり上げて泣いてしまった。
しろいぬ万呼