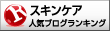[64]かなり専門的な美白の話 その4
やたら詳しい美白の話。第三段階目は「チロシンから多段階の反応を経てメラニン色素が作られる。」です。
もはや、よほど専門的な人か、よっぽど勉強熱心な美容ライターか美容オタクくらいしか対象になってない気もしますが、はじめてしまったので、このまま進めてしまいます。
ということで、メラニン。
チロシンというのは身体の中に存在するアミノ酸の一種です。ここにチロシナーゼという酵素が働くことで、ドーパという物質が作られ、さらに反応が進んでドーパキノンへ、そしてその先へ、と数段階を経てメラニンができます。この、変化そのものに作用して、メラニン生成を止めるという仕組みがあります。
これらの反応が酸化反応であるため、基本的には還元力(抗酸化力)のある成分を配合することで、酸化反応を抑制し、メラニン生成を抑制するというメカニズムが主なもの。ドーパキノンからドーパに還元してやることで、メラニン生成反応をその辺で止めてしまうというのが、シンプルなメカニズムです(実際には、もう少しややこしいみたいですが)
代表的なのはビタミンC。ただし、単体だと、メラノサイトにたどり着く前に活性を失うので、ビタミンC誘導体を配合するのが一般的です。医薬部外品の主剤として認可されているのは、Mg、Na、アスコルビル、VCIP(テトラヘキシルデカン酸←長いので覚えなくていいです)、エチル(←もっとも新しいビタミンC誘導体です)、くらい。そのほかにもいくつかありますが、安定性が低くて実用に耐えないとか、いろいろ問題もあるようです。
抗酸化成分としては、これらのほかに、植物エキス系で美白作用を持つ成分が多数あります。割と信憑性が高いのはコケモモエキスで、これはアルブチンという成分を含んでいるからと説明されています。
アルブチンは資生堂が長いこと特許で抑えていた美白成分で、作用は穏やかですが、効果はあるようで、2年近くにわたり、数百名のモニターを追いかけたレポートを読んだことがあります。アルファ型とベータ型があり、資生堂が使っていたのはベータ型。レポートではアルファ型の方が効果が高いとなっていますが、S社さんが、その辺を見落としているはずはないので、なにかほかに理由があったのではないか、というのが、うがった見方をするベテラン研究員の見方のようです。(真相は不明)
アルブチンは、実はハイドロキノンという成分の誘導体にあたります。ハイドロキノンは、その関連の話だけで2本くらいかけてしまうので、これは別の機会にするとして、親戚筋みたいな成分でルシノール(ポーラ)、エラグ酸(ライオン)などがあり、レゾルシノールとその誘導体も、このグループに入れる人もいます。そのほか、フェルラ酸とか抗酸化による美白機能は多くあります。
アルブチンは、論文によると、還元反応ではなく、競合阻害とされていて、ちょっとメカニズムが違うようなのですが、最近は、その辺の説明があんまりされてないようなので、ここでもあんまり追求しないことにします。
人体の中で、酸化反応というのは、常に起こっていて、これが肌の老化に大変大きな役割を果たしていることが知られています。美白成分として知られるビタミンCですが、酸化防止剤という観点で見ると、常に肌に与えておくのはよいことだと思われます。美白作用としては、ちょっと弱いという印象ですけどね。
ということで、次の段階に入ります。
トミナガ☆マコト
【関連記事】
[63]かなり専門的な美白の話 その3